
「ポンペイ展」は、宮城展が9月25日に終わり、10月12日からは、ファイナルとなる福岡展が始まります。ポンペイ展は、東京、京都、宮城、福岡と巡回しています。このページでは、東京展の写真を交え、見どころと楽しみ方をお伝えします。
著者 JTB運営・旅行地理検定合格。旅行取材年80日。
・
結論ファースト
ポンペイ展に来る、半分くらいは映画『ポンペイ』を見た方(女性が多い)ですが、もちろん見ていなくても楽しめます。ポイントは次の2つです。

ポンペイは、火山噴火で壊滅したローマの都市です。日本が「弥生時代」だったころの話だと知っておくと、暮らしや芸術、医学の発達に非常に驚きます。

ポンペイ展の人気モチーフは、発掘された「焦げたパン」です。1000年以上、火砕流堆積物の下に埋まっていたポンペイですが、世界を驚かせたのが、火砕流で焦げたパンがそのまま出てきたこと。お土産も「焦げパン」「焦げモノ」が大人気です。
ポンペイ展の予約
なお、映画『ポンペイ』を見ておきたい場合、ユーネクストをクリックし、ポンペイで検索し、掲載があれば無料トライアルで見られます。
ポンペイとは?


ポンペイは、ローマの都市です。日本が弥生時代だったころ、驚くほど近代的な都市が形成されていました。
しかし、西暦79年、ヴェスビオ山の噴火にによる火砕流と火砕サージ(火山灰と空気の混ざった高熱の爆風)で町ごと埋まってしまいます。
※東京、京都、宮城、福岡の展示物は同等ですが、一部異なる場合があります。

1000年以上、火砕流堆積物の下に埋まっていたポンペイですが、その後発掘が開始。火砕流堆積物には乾燥剤に似た成分が含まれ、湿気を吸収したため、多くのモノが原型を留めて出土し、世界を驚かせました。

ガラスも出土しています。

出土した水道管です。日本は弥生時代であり、井戸と水路で暮らしていた頃、水道が張り巡らされていたのです。

芸術も、想像を超えた発達を示していました。

芸術作品に用いた塗料です。

若者役の俳優の像。何と、劇場まであったのです。このほか、公衆浴場もあり、現在と大差のない暮らし方をしていたようです。

医学の発展も、驚くべき水準。

はかりです。商取引が発達していたことが想像できます。
人気の出土品が焦げたパン


ポンペイ展で、もっとも人気があるのが、焦げたパンです。
ポンペイでは、当時パン屋さんが20軒ほど営業していたことが分かっています。日本では、ようやく稲作が全国に普及したばかりの頃。売られていたパンは、焦げてはしまいましたが、奇跡的にそのまま出土しました。

パン屋を描いた絵画も出土。パンの形が同じです。

大人気のお土産が「焦げパン」グッズ。

「焦げモノ」も人気です。
ポンペイ展の予約

映画『ポンペイ』を見ておきたい場合、ユーネクストをクリックし、ポンペイで検索し、掲載があれば無料トライアルで見られます。
関東となりますが、「日本のポンペイ」と言われる鎌原村がブラタモリ浅間山編で紹介されています。
もう少し深く

このページの内容では物足りないという方は、上の絵画の意味を考えてみては? メメントモリを象徴する絵画の1つですが、上の絵画の具体的な意味を考えてみても楽しめそうです。
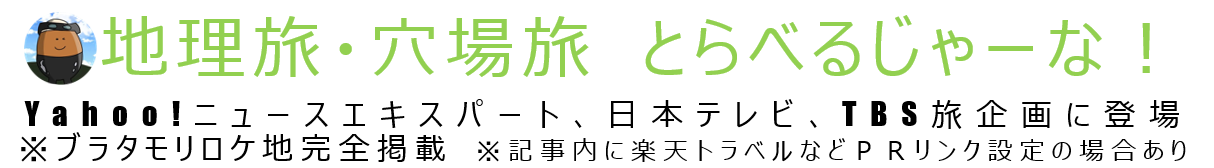
コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)