
NHK番組のブラタモリで、松江の歴史や地形を踏まえた見どころが紹介されました。旅行の備忘録や教養のためにぜひご利用ください。このページでは、松江のブラタモリ紹介地へのアクセスや関連情報を扱っています。

世界最古のやどを見る
世界最古の宿・ギネスブック認定 全館源泉掛け流し 西山温泉 慶雲館(楽天トラベル)
松江市とは

松江市は、宍道湖沿いにある山陰地方最大の都市。東側にある米子市と、一体化した経済圏を築いています。宍道湖や川に象徴されるため水の都と称されることもあります。
2015年に松江城の天守閣は国宝に指定されています。姫路城、彦根城、犬山城、松本城に続いて5番目。最後に指定された松本城、松江城は、人気がある黒い城です。
黒い城は、豊臣秀吉の大阪城に倣ったと言われ、技術的には白(白漆喰)より易しいですが、経済性や耐久性に優れています。
松江城の北側にある、塩見縄手通りが観光の拠点です。
国宝・松江城/ブラタモリ松江


ブタラモリ松江編は、国宝指定を祝う看板が立つ松江城からスタート。松江は松江城ができて初めて栄えた町。築城の様子を知ることが、町を知ることになります。日本に現存する12の天守閣のひとつです。
松江城天守閣の1階には、天守閣には珍しい井戸があります。しかしガイドは、井戸よりも見てほしい穴があると言います。柱に開いた小さなくぎ穴です。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿
赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)
松江城が国宝に指定されなかったのは、歴史が不明確だったからです。大捜索ののち、創建年を明らかにする札が、近くの松江神社で見つかりましたが、松江城のものである証拠がありませんでした。その後、柱に開いた小さなくぎ穴と札に開いた穴の大きさが一致。ようやく国宝指定の条件が揃いました。

松江城の天守閣からは宍道湖が見えます。松江一帯は、江戸時代初期の築城までは、宍道湖を中心とする低湿地の寒村でした。
当時、月山富田城という山城が築かれていましたが、防衛には固いものの交通が不便で、関が原の戦いの後1607年から松江城の築城が始まりました。
松江城の原点は、宍道湖東の白潟|ブラタモリ松江
ブラタモリは、松江城を南下、松江大橋を渡り、白潟と呼ばれる住宅地を歩きます。
白潟と呼ばれる地区(地図●印)は、微高地、つまり僅かな高台となっています。
湿地帯のなかでは貴重な土地で、江戸時代初期の築城以前にも、多くの人が住んでいまいした。そして、築城の拠点として利用され、そのまま町家(商業地)として城下町の一部となりました。
白潟には廻船問屋が軒を連ねました。ブラタモリは、かつて廻船問屋だった旧家を訪ねます(地図●印)。松江藩から交付された、船の通行証が保存されています。

マツコが「泊まりたい」と2度発言した宿
赤倉温泉 赤倉観光ホテル(楽天トラベル)
松江城周辺の堀|ブラタモリ松江
県立松江北高校が立つ高台と、松江城が立つ高台(亀田山)は、築城前には尾根でつながる地続きの状態でした。築城の際、尾根を切り崩し、膨大な盛り土を生み出すと同時に、堀が作られました。松江城築城の最大の難所です。
松江城には、堀が多くあります。防衛のほか、湿地帯の排水、盛り土づくりの役割を果たしました。
ブラタモリは、堀をめぐるチャーター船に乗船します。赤で示した航路は、一般の人も利用できる堀川遊覧船の遊覧コースの一部(所要50分)、青で示した部分は、ブラタモリ独自のルートです。
- 松江城へ渡る橋を通過する際には、可動式の屋根が少し低くなります。
- また松江城の南には、一段低い石段があります(地図●印、堀川遊覧船は通りません)。武家屋敷にあった、船入(船置き場)の痕跡です。
- チャーター船は、最後に船入の跡に到着します(地図●印、松江駅から徒歩10分)。

堀川遊覧船
松江と治水|ブラタモリ松江
現在の松江も、水害のリスクが高い町です。松江市役所前の強力な排水ポンプで、堀川の推移をコントロールしています。川が浅く橋が低いため、水位が狂うと堀川遊覧船も通行できなくなってしまうのです。
- 国交省松江堀川浄化ポンプ場 松江しんじ湖温泉駅(出雲大社方面始発駅)から徒歩3分。

宍道湖は浅くすぐにあふれだしてしまいます。工事で川幅を広げられた大橋川は、日本海に水を逃がすという、大きな役割を担っています。その副産物として海水が流入し、宍道湖全域での名物のしじみの収穫に結びつきました。しじみの漁獲量は現在日本一です。
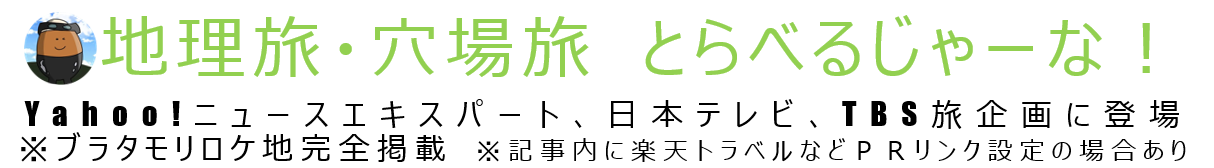



コメントをどうぞ(情報ご提供、旅行相談など)